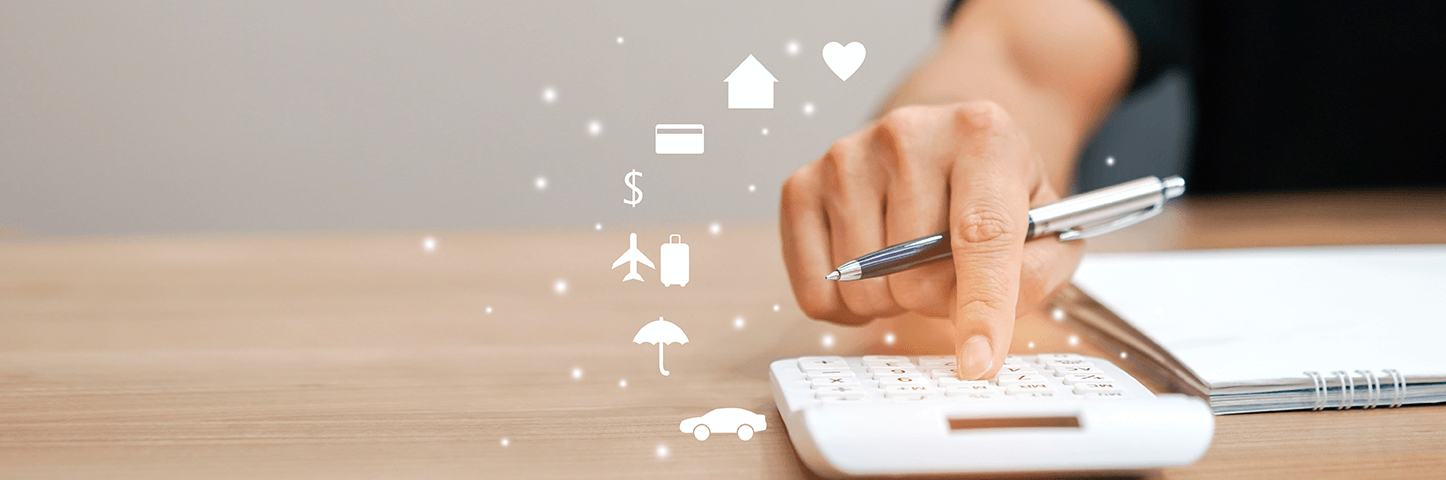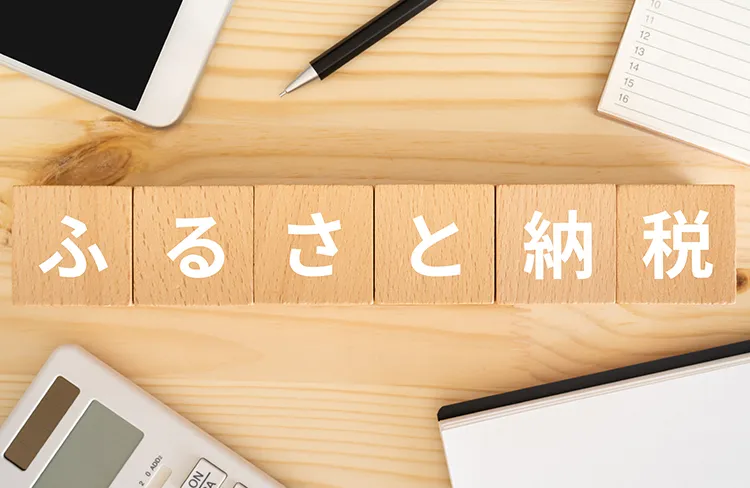NISAは資産形成の有効な手段として注目を集めています。年間投資枠の拡大や非課税期間の無期限化等、制度面での充実により、より柔軟な資産形成が可能となっています。一方で「メリットばかりが強調されているのではないか」「本当に自分に適しているのか」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、NISAのデメリットを含めた特徴を解説し、失敗しない資産形成のポイントをお伝えします。

1. NISAとは

NISAは個人投資家のための税制優遇制度です。通常、投資で得た運用益には約20%の税金がかかりますが、NISA制度を利用すれば、非課税となります。投資信託などで運用して得た利益を、税金を差引かれることなく受取ることができます。
「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの非課税投資枠で構成されており、それぞれの投資枠で年間投資枠や投資対象商品、購入方法が異なります。
NISA制度のくわしい内容は、「NISA(ニーサ)/新NISAで資産運用をもっと有利に」をご覧ください。
2. NISAで注意したいデメリットとは

NISAは魅力的な投資制度ですが、その特徴をよく理解しておく必要があります。NISAを活用する際に気をつけるべきポイントについてくわしく見ていきましょう。
口座開設は18歳以上、1人1口座まで
NISA口座は、開設する年の1月1日時点で満18歳以上の日本居住者が対象です。1人1口座という原則があり、金融機関の変更は年1回までに制限されています。そのため、口座を開設する金融機関は慎重に選択することが大切です。
口座開設前に取扱商品の種類と手数料、お住まいの近くに店舗があるか、相談のしやすさ等を比較検討する必要があります。特に投資初心者の方は、手厚いサポートを受けられる金融機関を選ぶことで、安心して資産形成を進めることができます。
投資対象商品が限定される
NISA制度では、購入できる投資商品に一定の制限があります。特につみたて投資枠では、低コストで長期投資と分散投資に適しているという金融庁の基準を満たす投資信託が対象となります。投資対象商品が厳選されているため投資がはじめての方でも選びやすく、安心してつみたて投資を始められます。また、成長投資枠の商品も個別株式や一定の基準を満たした投資信託に限定されます。成長投資枠で購入できる投資信託は、毎月分配型でないこと、信託期間が20年以上あること、デリバティブ取引を用いた投資信託でないことが条件となっています。
元本を下回るリスクがある
NISAで購入できる金融商品には元本保証がなく、市場の変動により投資した金額を下回るリスクがあります。たとえば株式投資では、企業業績の悪化や市場全体の下落により、投資した金額を割り込む可能性があります。
このようなリスクにそなえるため、投資に関する理解を深め、十分な知識を身につけることが大切です。また、一時的に価格が下がったとしても売却しなければ損失が確定する訳ではありません。万が一損失が生じても生活に影響が出ないよう、余裕資金での運用を心がける必要があります。
投資配分や売買のタイミングを自分で判断する必要がある
NISAでは、月々の投資額の設定や投資枠の使い分け、売買のタイミング、運用方針の見直し等、様々な判断が必要です。適切な判断をするためには、将来の資金需要を見据えた目標設定と投資計画が重要です。たとえば、老後の生活資金として2,000万円が必要、という目標設定をする場合、運用できる期間、毎月の積立可能額から目標を達成するための期待リターンを逆算することができます。また、この投資計画にNISA枠を活用することで、得られた利益から税金を差引かれることなく受取ることができます。運用中は、目標に向けた運用状況を確認しながら、売却のタイミングも自身の判断で決める必要があります。
さらに、定期的に運用状況を確認しながら、ライフプランにあわせて投資方針を見直していくことが、着実な資産形成につながります。
3. デメリットばかりじゃない!NISAのメリット

NISAには注意すべきデメリットがありますが、それ以上に魅力的なメリットが存在します。投資を始める方に知っていただきたいNISAのメリットについて解説します。
投資初心者でも始めやすい
NISAは、投資初心者でも始めやすい制度として設計されています。池田泉州銀行では毎月5千円からの積立投資が可能で、手軽に始められる点が特徴です。
特につみたて投資枠は、金融庁が認定した低コストで長期・分散投資に適した投資信託のみが対象のため、商品選びの負担が少なく、安心して投資を始められます。また、定期的な積立投資により、市場の変動リスクを抑えながら資産形成を進めることができます。
非課税保有期間が無期限のため長期投資に最適
NISAでは非課税保有期間が無期限のため、時間をかけてじっくりと資産を育てることができます。たとえば、30代から毎月3万円ずつ積立てを始め、退職後の生活資金として2,000万円を目指すといった長期の目標に適しています。
運用益を再投資することで複利効果が期待でき、また一時的な含み損が発生しても非課税期間が無期限であるため価格回復を待つという選択が可能です。経済成長のパワーを長期の資産運用でしっかりと取込み、非課税メリットを活かした資産形成を行いましょう。
非課税枠の再利用等、柔軟な投資が可能
NISAには、保有資産を売却した場合でも、その投資枠を再利用できるしくみがあります。NISA制度で投資した商品を売却すると、その分の投資枠が翌年に復活します。ただし、復活する投資枠は売却時の金額ではなく「購入時の取得価格分」の非課税枠です。たとえば、100万円で購入した資産が150万円に値上がりして売却しても、翌年に復活する枠は購入時の100万円分です。
非課税枠の再利用により、生活資金が必要になった際の一部売却や、運用方針の見直し等、状況に応じた柔軟な資産運用が可能です。
4. NISAで失敗しない資産形成のポイント

NISAで長期的な資産形成を目指すうえで押さえておきたい3つのポイントを解説します。
長期視点で運用する
長期的な視点でNISA投資を行うことで、複利効果による資産形成が期待できます。複利効果とは、得られた利益を再投資することで、その利益からさらに利益が生まれるしくみです。
たとえば、100万円の投資額に対し5%の利益が出た場合、次は105万円に対し利益が発生します。さらに翌年も5%の利益が出れば110万2,500円に、3年目は115万7,625円というように、利益の上に利益が重なっていきます。このように投資期間が長くなるほど、元本に利益が積み重なり、資産の成長が加速していく可能性があります。
NISAは非課税期間が無期限のため、30年、40年といった長期にわたって複利効果を最大限活用できます。若い世代から始めることで、将来の資産形成に大きな効果が期待できる制度です。
コツコツ積立てる
NISAで資産形成を成功させるには、コツコツ積立てることが大切です。毎回、決まった金額で金融商品等を購入する「ドルコスト平均法」は、投資リスクを抑える効果的な方法です。
ドルコスト平均法では、商品価格が下がったときは同じ金額でより多くの数量を購入でき、反対に価格が上がったときは購入数量が少なくなります。このように価格に応じて自動的に購入数量が調整されることで、平均の購入価格を抑え、高値づかみのリスクを避けられます。
投資初心者にとって、いつ買うべきか、いくら投資すべきかの判断は難しいものです。しかし、毎月決まった金額を投資する方法なら、相場の動きを気にせず継続的な投資が可能です。長期的な視点で着実な資産形成を目指せます。
分散投資をする
資産形成を成功させるためには、分散投資を意識しましょう。特定の商品に集中投資をすると、その商品の価格変動が資産全体に大きな影響を与える可能性があります。異なる種類の商品に分散して投資することで、リスクを軽減できます。
NISAでは、つみたて投資枠・成長投資枠のどちらでも、分散投資に適した投資信託を購入できます。そもそも投資信託は、1つのファンドの中で複数の企業の株式や複数の地域に、また株式や債券といった複数の資産に分散投資を行うしくみになっているため、1つの商品でも分散効果が期待できます。投資初心者の方でも、手軽にリスクを抑えた運用を始めることができます。
5. まとめ

NISAでは非課税期間が無期限となり、長期的な資産形成に活用できます。メリット・デメリットを十分理解したうえで、必要に応じて専門家に相談しながら、自分に合った投資方法の選択が大切です。
口座開設を行う年の1月1日時点で18歳以上であれば、どなたでもNISAを利用できるため、資産形成の第一歩として検討してみてはいかがでしょうか。池田泉州銀行では資産形成や将来的なマネープランに関する相談を承っておりますので、NISAの活用をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
注目カテゴリワード
気になるカテゴリワードから
知りたい情報をみつけよう