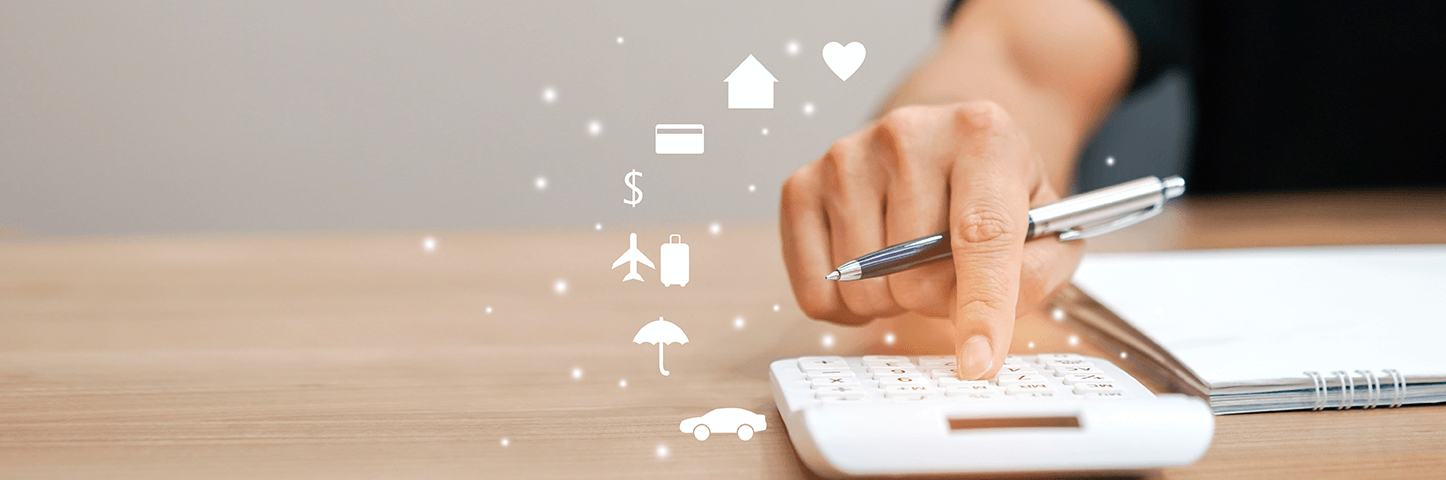税制優遇が魅力のNISA制度。「確定申告は必要なの?」「年末調整で何か手続きは必要?」など、税務面での疑問をお持ちの方も多いでしょう。
NISAは基本的に確定申告や年末調整は不要ですが、一定の条件下では確定申告が必要となるケースがあります。
本記事では、NISAにおける確定申告と年末調整の基本的なルールを解説します。また、確定申告が必要となる具体的な条件や、税務上の注意点についても、わかりやすくご紹介します。
NISAは年末調整や確定申告が原則不要!まずはNISA制度のしくみやポイントを知ってから始めよう!
NISA口座の開設はアプリまたは窓口でのお手続きとなります。
1. NISAは年末調整が不要

NISAは年末調整が不要です。年末調整とは、給与所得者の1年間の所得税を精算する手続きです。
NISAは非課税制度のため、運用益が発生しても課税対象とはならず、会社への報告は必要ありません。また、年末調整時の各種控除や税額計算にも影響を与えることはありません。
2. NISAは確定申告も原則不要
NISA口座での運用益は、原則として確定申告も不要です。確定申告とは、1年間の所得と、それに対する所得税額を確定させるための手続きのことを指します。
通常、投資による収益は課税対象となり確定申告が必要になることがありますが、NISAは非課税制度のため、運用によって得た利益については税金が発生しません。
3. NISAで確定申告が必要となる条件

NISAは原則として確定申告が不要ですが、次のようなケースでは確定申告が必要になる場合があります。
「株式数比例配分方式」以外の方法で受け取る場合
証券会社のNISA口座で配当金や投資信託の分配金を非課税で受け取る場合、「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。「株式数比例配分方式」とは、配当金や分配金を証券会社の口座で受け取る方法のことです。
NISA口座での投資であっても、配当金や分配金の受取方法が「株式数比例配分方式」以外の場合、配当金やETF、REITからの分配金には約20%の税率で源泉徴収が行われ、課税対象となります。
株式数比例配分方式以外の受取方法としては、以下の3つの方式があります。
- 登録配当金受領口座方式
- 個別銘柄指定方式
- 配当金領収証方式
これらの方式を選択して課税対象となった場合でも、必ずしも確定申告が必要というわけではありません。ただし、次の場合には確定申告が必要となります。
- 総合課税により配当控除の適用を受ける場合
- 申告分離課税で譲渡損失の損益通算や繰越控除を利用する場合
非課税期間が終了し、課税口座へ移管した場合
2023年までのNISA制度で運用中の資産は、非課税期間が終了すると自動的に課税口座へ移管されます。2023年までのNISAでは、一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年間と非課税期間が設けられています。
移管後はそれまで非課税だった運用益が課税対象となり、場合によっては確定申告が必要となる可能性があります。保有している商品の非課税期間の満了時期を確認しておきましょう。
\まずは、NISAを正しく知ることから/
NISA口座の開設はアプリまたは窓口でのお手続きとなります。
4. NISAの確定申告の注意点

NISAでの資産運用において、確定申告時に注意すべきポイントについて解説します。非課税口座であるNISAは、所得控除や投資損失の取り扱いなど、通常の課税口座とは異なる特徴があります。
所得控除が受けられない
NISAの投資元本は、確定申告時の所得控除の対象とはなりません。所得控除とは課税所得から一定額を差し引いて税負担を軽減するしくみです。一方、iDeCoでは掛け金が全額所得控除となり、所得税・住民税の負担を軽減できるメリットがあります。
損益通算や繰越控除ができない
NISA口座は非課税制度のため、損益通算や繰越控除の対象外です。課税口座では、年間の投資で生じた利益と損失を相殺する損益通算や、損失を最長3年間繰り越せる繰越控除が可能です。しかし、NISA口座は非課税制度であるため、NISA口座での損失をほかの課税口座の利益と相殺したり、翌年以降に繰り越したりすることはできません。
NISAの運用益は扶養控除や配偶者控除に影響しない
NISAで得た運用益は、扶養控除や配偶者控除における所得判定の対象外です。これらの控除を受けるためには、扶養家族の年間所得を一定額以下に抑える必要がありますが、NISA口座での収益は年間所得の計算に含まれません。
そのため、家族がNISA口座で投資収益を得ても、扶養控除や配偶者控除の適用に影響を与えることはありません。所得制限を気にすることなく、NISAでの資産形成が可能です。
5. 資産運用で確定申告が必要な場合とは?

これまでNISA口座における確定申告の要否について解説してきましたが、資産運用全般における確定申告の必要性についても把握しておきましょう。
確定申告の要否は、口座の種類や取引内容によって異なります。以下では、資産運用において確定申告が必要となる代表的なケースをご説明します。
一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で運用益が出ている場合
一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で投資を行い、運用益が発生した場合は確定申告が必要です。一般口座では、投資家自身が損益計算から確定申告、納税までのすべての手続きを行う必要があります。
一方、特定口座(源泉徴収なし)では、金融機関が損益計算と年間取引報告書の作成を代行しますが、確定申告と納税は本人が行います。
複数の一般口座や特定口座との間で損益通算を行う場合
複数の証券口座間で損益通算を行う場合は、確定申告が必須となります。損益通算とは、同一年度内で発生した投資の利益と損失を相殺する制度です。
たとえば、ある証券会社の一般口座で発生した損失と、別の証券会社の特定口座で生じた利益を相殺したい場合は確定申告により両者を合算し、課税対象となる利益を減らすことができます。
悩んだら相談できる安心感!NISA口座開設は窓口のある金融機関がおすすめ!
NISA口座の開設はアプリまたは窓口でのお手続きとなります。
6. まとめ

本記事では、NISAの確定申告に関する基本ルールと、申告が必要となる例外的なケースについて解説しました。NISA口座は原則として非課税制度であり、通常の確定申告は不要です。ただし、配当金の受取方法や非課税期間終了後の資産移管など、特定の状況下では確定申告が必要となるケースがあります。
池田泉州銀行の窓口では、投資信託やNISAに関するご相談から口座開設まで承っております。また、住居費や教育費の準備、退職金の運用、相続対策など、長期的な資産形成に関する幅広いご相談にも対応させていただいております。
大切なお金のことだからこそ、迷ったときや困ったときは、お気軽に担当者へご相談ください。アプリやWEBからの来店予約サービスをご利用いただくと、優先的にご案内させていただきます。ぜひご活用ください。
\まずは、NISA口座の開設から始めよう/
NISA口座の開設はアプリまたは窓口でのお手続きとなります。
注目カテゴリワード
気になるカテゴリワードから
知りたい情報をみつけよう