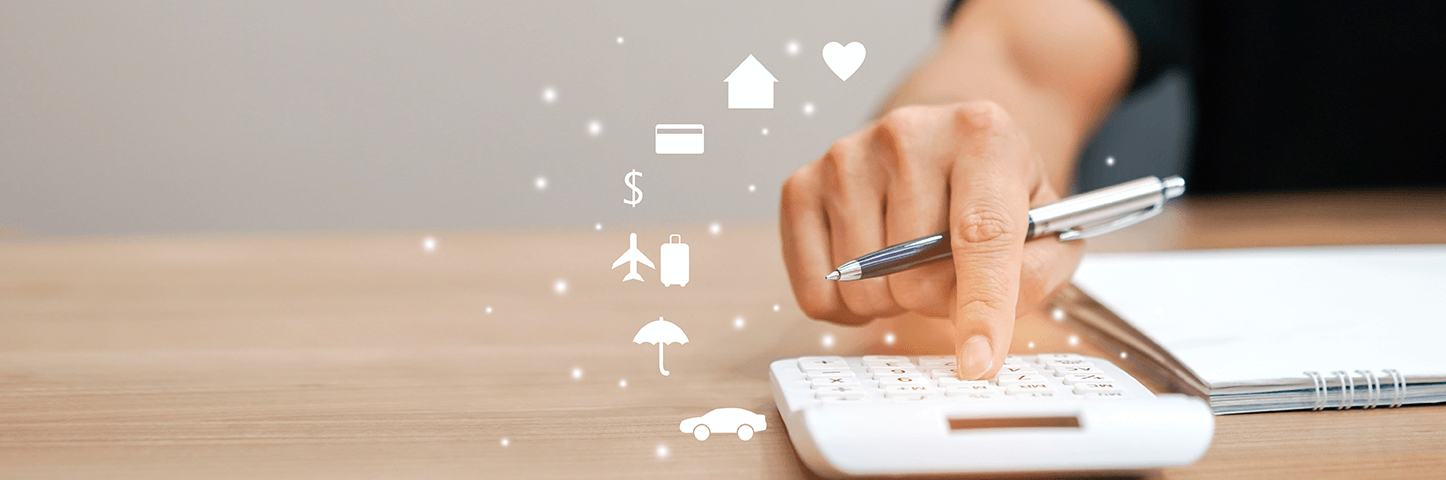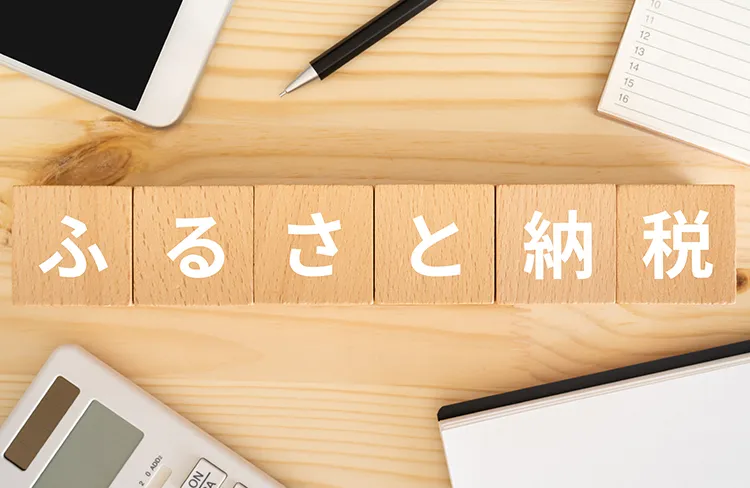資産形成の支援制度として注目を集めるNISA。毎年一定額まで株式や投資信託等に投資でき、投資した金融商品から得られる利益が非課税になるため、長期的な資産運用に役立つ制度です。しかし、「難しそう」「投資自体に不安がある」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、投資の経験がない方でも理解できるよう、NISAの基本的なしくみから、具体的なメリット、実際の始め方まで、わかりやすく解説します。
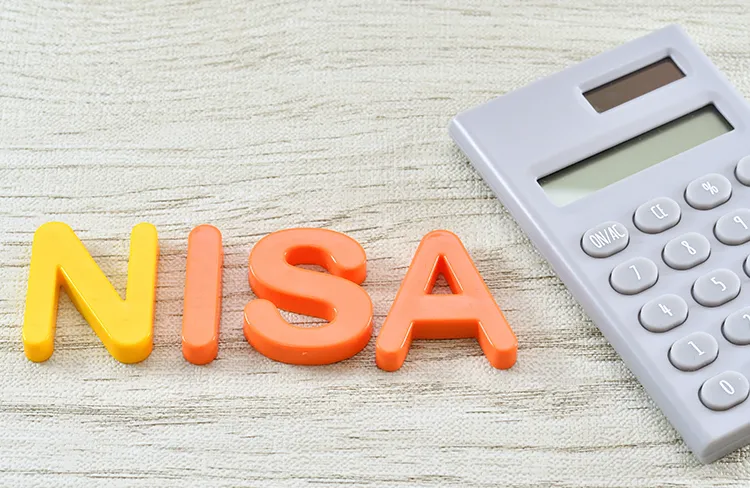
1. NISAとは、投資で得られた収益に税金がかからない制度

NISAは、国が定めた税制優遇制度です。投資で得られる運用益には通常20.315%の税金がかかりますが、NISA口座で投資するとこれが非課税となります。投資枠には2種類あり、定期的に一定額を購入する積立投資専用のつみたて投資枠と、より幅広い商品に投資でき一括でも積立でも購入ができる成長投資枠があります。この2つの枠を活用することで、効率的な資産形成を目指せます。
つみたて投資枠と成長投資枠についてくわしく知りたい方は、「つみたて投資枠と成長投資枠の違いは?それぞれの特徴や選び方を解説」も参照ください。
2. NISAのメリット

運用益に税金がかからないことは、NISAの大きなメリットです。それ以外にも資産形成する上で魅力的なポイントがいくつかあります。
年間最大360万円まで非課税投資が可能
NISAの年間投資上限額は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円で両枠の併用により合計で年間360万円です。また生涯では、最大1,800万円まで非課税で運用が可能です。
投資期間は無期限
NISAでは、投資した商品を無期限で非課税運用できます。お子さまの教育資金や退職後の生活資金などに備えて、計画的に資産形成を進められます。ライフプランや経済状況の変化にあわせて柔軟に運用方針を見直すことも可能です。
投資商品の選択肢が充実
NISAは投資目的や運用スタイルに応じて、幅広い商品から選ぶことができます。つみたて投資枠では長期の資産形成に適した投資信託がラインアップされており、定期的な積立が可能です。一方、成長投資枠では、幅広い投資対象から自由に選択でき、さまざまな投資信託や個別の株式に投資することができます。両方の枠を組み合わせることが可能で、コツコツ積立投資と、好きなタイミングでの一括投資を組み合わせた運用が可能です。
売却後も非課税枠を再利用できる
NISAでは、保有する投資商品を売却しても、取得金額分の非課税枠が翌年以降に再度利用できます。NISAで保有している商品を売却した場合、翌年以降売却した商品の簿価(取得金額)の分だけ非課税投資枠が復活し、再利用が可能になります。
ただし、再利用する非課税枠は、年間投資上限額360万円(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)の範囲内で利用することになります。非課税枠の再利用により、資金が必要になった際の取りくずしや、投資商品や資産配分の見直し等を柔軟に行うことができます。
3. NISAの注意点

多くのメリットがあるNISAですが、利用にあたって気をつけるべきポイントがあります。
元本保証がない
NISA利用に限らず投資には、市場の変動により投資した金額を下回るリスクがあります。投資商品は、預貯金のように元本が保証される商品ではありません。ただし、分散投資や長期投資の考え方を取り入れることでリスクを抑えながら、預貯金以上の収益を期待することができます。特につみたて投資枠の対象商品は、「長期・積立・分散」投資に適した金融庁の基準を満たす投資信託に限られています。対象商品が厳選されているので、初心者の方にも選びやすいのが特徴です。
投資枠の使い方や売却タイミングを自分で決める必要がある
NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠のどちらを使うか、いくら投資するか、いつ売却するか等、自分で判断する必要があります。
投資が初めての方は、つみたて投資枠で少額から積立投資をスタートするのがおすすめです。投資に慣れてきたら積立額を増やしたり、成長投資枠の活用を考える等、焦らず自分のペースで投資を広げていくことができます。
4. NISA初心者へのアドバイス

NISAを活用して資産形成を始める方に、3つの重要なポイントをお伝えします。
投資目標を設定する
まずは投資の目的を具体的に考えましょう。老後の生活資金、子どもの教育費、マイホーム購入等、目標が決まれば必要な金額や投資期間も見えてきます。目標金額と期間が分かれば、月々の投資額が逆算できるようになります。
長期的な視点で運用する
NISAは長期の資産形成を支援する制度です。金融商品は短期的には大きく価格変動することがありますが、時間をかけることでその影響を抑えることができます。そのため、日々の値動きに一喜一憂せず、長期的な視点で投資を続けることが大切です。また、投資の期間が長いほど運用で得た利益を次の投資に組入れて運用し、元本を増やす「複利運用」の恩恵を受けることができます。
分散投資を行う
投資は一つの商品や市場に集中せず、複数の地域や資産に分けることが重要です。投資信託は、多数の投資家が金融機関を通じて資金を出し合って、まとめられた資金を運用の専門家が株式や債券など様々な資産に投資、運用するしくみです。たとえば、株式と債券では異なる値動きをすることが多く、組み合わせることで投資全体のリスクを抑えることができます。
5. NISAのはじめかた

NISAでの投資を始めるには、いくつかの準備とお手続きが必要です。NISA口座の開設から投資商品の選び方まで、資産形成を始める手順を見てみましょう。
金融機関を選ぶ
NISAを始めるには、銀行、証券会社等の金融機関でNISA口座を開設します。ただし、NISA口座は一人につき一つしか開設できず、つみたて投資枠と成長投資枠も同じ金融機関で利用することになります。取引のしやすさ、サポート体制、取扱商品の数、手数料の水準等を総合的に比較して、自分に合った金融機関を選びましょう。
NISA口座を開設する
NISA口座の開設には、以下の書類等が必要です。
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード)
- 本人確認書類
- 届出印(銀行・対面型証券会社の場合)
ただし、必要な書類は金融機関によって異なる場合があります。証券会社や銀行、またインターネットや店頭等、お申込みの方法に応じて必要書類が変わりますので、あらかじめ確認しておきましょう。
提出された書類は金融機関で確認後、税務署で審査され、承認後にNISA口座が開設されます。
投資する商品を選んで購入する
NISA口座が開設されたら、商品を選んで購入します。
商品選びの際は、運用コストや過去の運用実績、投資対象の分散度合い等を確認し、自分の投資目的やリスク許容度に合った商品を選びましょう。
6. まとめ

NISAは、将来に向けた資産づくりを支援する非課税投資制度です。つみたて投資枠で年間120万円、成長投資枠で年間240万円、合計360万円まで非課税で投資できます。投資期間に制限がなく、売却後の投資枠も再利用できるため、長期的な視点での運用が可能です。投資初心者は、金融庁の基準を満たし、低コストの商品が揃うつみたて投資枠から始めるのがおすすめです。また、自分に合った商品の選び方や月々の積立金額をいくらにすればよいか迷ったり、運用開始後の値動きへの対処方法や手続きに不安や疑問を感じたりすることもあるでしょう。商品選びや投資枠の使い方、ライフイベントに応じた見直し等、不安な点については相談窓口のある金融機関で専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
池田泉州銀行では、お客さまの目標に合わせた投資プランを丁寧にご提案します。また、住宅ローンや教育資金等、ライフプラン全般のご相談も承っておりますので、お近くの窓口までお気軽にお立ち寄りください。
注目カテゴリワード
気になるカテゴリワードから
知りたい情報をみつけよう